-
所属(所属キャンパス)
-
研究所・センター等 産業研究所 ( 三田 )
-
職名
-
教授
-
メールアドレス
-
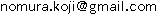
野村 浩二 ( ノムラ コウジ )
NOMURA Koji
慶應義塾大学, 産業研究所(KEO), 助手
ハーバード大学, ケネディスクール(KSG), CBGフェロー
慶應義塾大学, 産業研究所(KEO), 准教授
内閣府, 経済社会総合研究所(ESRI), 客員主任研究員
経済協力開発機構(OECD), 科学技術産業局(STI), エコノミスト
北海道立函館中部高校
卒業
慶應義塾大学, 商学部
大学, 卒業
慶應義塾大学, 商学研究科
大学院, 修了, 修士
慶應義塾大学, 商学研究科
大学院, 単位取得退学, 博士
APO Productivity Databook 2025
Koji Nomura and Mun S. Ho, Asian Productivity Organization, Keio University Press, 2025年09月, ページ数: 219
Koji Nomura, Contemporary South Asian Studies, Springer, 2025年05月, ページ数: 259
Energy Productivity and Economic Growth: Experiences of the Japanese Industries, 1955–2019
Koji Nomura, Springer, 2023年01月, ページ数: 268
杉山大志、野村浩二、岡芳明、岡野邦彦、加藤康子、巽直樹、田中博、戸田直樹、中澤治久、南部鶴彦、平井宏治、松田智、薬師院仁志、山本隆三、小島正美、澤田哲生、室中善博、山口雅之、渡辺正, 2025年09月, ページ数: 224
Measuring Real Energy Price Gaps: The Real PLI Framework for Competitiveness Monitoring
Nomura K., Inaba S.
Sustainability Switzerland 18 ( 1 ) 2026年01月
研究論文(学術雑誌), 共著, 責任著者, 査読有り
"Measuring Real Energy Price Gaps: The Real PLI Framework for Competitiveness Monitoring"
Koji Nomura and Sho Inaba
Preprints.org 2025年11月
研究論文(研究会,シンポジウム資料等), 共著, 責任著者
"Productivity Dynamics in the Maldives: A First Outlook Based on the Maldivian Productivity Accounts, 1970–2023, with Comparisons to SAARC and Fiji"
Koji Nomura
(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) 2025年10月
研究論文(その他学術会議資料等), 単著
"Bhutan’s Productivity Trends, 1990–2023: Findings from Bhutanese Productivity Account 2025"
Koji Nomura
(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) 2025年08月
研究論文(その他学術会議資料等), 単著
"Bhutan’s Productivity Stagnation: Hydropower and Beyond"
Koji Nomura
Hydropower-Led Economic Growth in Bhutan (Springer) 207 - 237 2025年05月
論文集(書籍)内論文, 単著
ポストパンデミックのエネルギー価格高騰と実質格差拡大 : 主要7か国の比較分析
野村, 浩二
KEO discussion paper (Keio Economic Observatory Sangyo Kenkyujo) ( 185 ) 2025年03月
野村, 浩二
KEO discussion paper (Keio Economic Observatory Sangyo Kenkyujo) ( 184 ) 2025年02月
入札データに基づく公共土木産出価格の測定 : 1989–2021年
野村, 浩二
KEO discussion paper (Keio Economic Observatory Sangyo Kenkyujo) ( 173 ) 2022年10月
Measurement of labor shares and quality-adjusted labor inputs in Vietnam, 1970–2018
野村, 浩二
KEO discussion paper (Keio Economic Observatory Sangyo Kenkyujo) ( 156 ) 2020年12月
Benchmark 2011 integrated estimates of the Japan-U.S. price level index for industry outputs
野村, 浩二
KEO discussion paper (Keio Economic Observatory Sangyo Kenkyujo) ( 144 ) 2018年10月
「境界に宿る日本」(時評ウェーブ)
野村浩二
『電気新聞』 (日本電気協会) 2025年12月
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア), 単著
「健全な懐疑」(時評ウェーブ)
野村浩二
『電気新聞』 (日本電気協会) 2025年11月
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア), 単著
「サナエノミクスに欠かせぬ脱炭素政策の転換―日米同盟の深化とエネルギー戦略」
野村浩二
『エネルギー政策研究会 EP Report』 (エネルギーフォーラム社) 2025年11月
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア), 単著
野村浩二
『月刊エネルギーフォーラム』 (エネルギーフォーラム社) ( 10月 ) 2025年10月
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア), 単著
「歪む市場」(時評ウェーブ)
野村浩二
『電気新聞』 (日本電気協会) 2025年09月
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア), 単著
「技術革新の社会実装は日本経済をどう変えるか―高解像度経済モデルBIPによる構造変化の可視化」
野村 浩二
[国内会議] RITE-ALPS IV 地球温暖化対策国際戦略技術委員会,
口頭発表(一般), 地球環境産業技術研究機構 RITE
「技術革新の社会実装に伴う経済成長、電力消費とCO2排出ー高解像度経済モデルBIPによる評価」
野村 浩二
[国内会議] RITE-ALPS IV 経済分析ワーキンググループ,
口頭発表(一般), 地球環境産業技術研究機構 RITE
「2040年の経済社会における技術革新の社会実装ー高解像度経済モデルBIPによる評価」
野村浩二
[国内会議] 「2040年の経済社会研究会」,
口頭発表(一般), SBI金融経済研究所
野村 浩二
[国内会議] 日本原子力学会シニアネットワーク連絡会(SNW) 第25回SNWシンポジウム「長期的な視点に立った骨太のエネルギー基盤を確立せよ!」,
公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等, 日本原子力学会シニアネットワーク連絡会(SNW)
「産業政策としてのエネルギー基本計画:実行可能性と制度的リスク」
野村 浩二
[国内会議] 日本機械学会「第7次エネルギー基本計画の複眼的考察~水素・再エネ・原子力のボトルネックと突破口~」,
公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等, 日本機械学会
APO Productivity Database (APO-PDB) 2026
野村浩二, 稲場翔, 中山紫央里
アジア生産性機構・慶應義塾大学産業研究所,
データベース, 共同
Asia Quality-adjusted Labor Input Database (AQALI) 2026
野村浩二, 稲場翔, 中山紫央里
慶應義塾大学産業研究所,
データベース, 共同
Multilateral Energy Cost Monitoring (ECM_202601)
Koji Nomura, Sho Inaba, and Mansaku Yoshida
Keio Economic Observatory, Keio University,
データベース, 共同
日経・経済図書文化賞
野村浩二, 2005年11月, 日本経済新聞社・日本経済研究センター, 『資本の測定-日本経済の資本深化と生産性-』
受賞区分: 出版社・新聞社・財団等の賞
義塾賞
野村浩二, 2005年11月, 慶應義塾大学
受賞区分: 塾内表彰等
経済統計各論(指数論)
2025年度
計量経済学特殊研究
2025年度
計量経済学特殊演習
2025年度
計量経済学演習
2025年度
研究会Qd
2025年度
「世界経済を考える―“遠いこと”から“自分ごと”へ」
令和7年度 埼玉県合同三田会 (慶應義塾大学 三田キャンパス)
,Technical Training Workshop on Productivity Account for Bhutan
Ministry of Finance, Royal Government of Bhutan, and UNESCAP, (Thimphu Deluxe Hotel, Thimphu)
,日本原子力学会 シニアネットワーク連絡会(SNW), 2025年度(第25回)SNWシンポジウム (国立オリンピック記念青少年総合センター)
,「境界に宿る日本」
電気新聞, 2025年12月
「健全な懐疑」
電気新聞, 2025年11月
「サナエノミクスに欠かせぬ脱炭素政策の転換―日米同盟の深化とエネルギー戦略」
エネルギーフォーラム, EPレポート, 2025年11月
"Kadin Helps Government Drive 8 Percent Economic Growth, Here's How"
VOI, Indonesia, 2025年11月
「長期的視点に立ったエネルギー政策を議論 SNWシンポジウム都内で開催」
原子力産業新聞, 2025年11月
Development of comprehensive aggregate productivity accounts for Asian countries, 1970-2023
Asian Productivity Organization and Keio Economic Observatory,
UNESCAP Project- Development of Growth Accounting Framework for Bhutan
Ministry of Finance and Keio Economic Observatory, (Ministry of Finance, Royal Government of Bhutan, and KEO, Keio University) ,
Barbara M. Fraumeni and Khuong M. Vu, (Telecommunications Policy) ,
Development of comprehensive aggregate productivity accounts for Asian countries, 1970-2022
Asian Productivity Organization and Keio Economic Observatory,
UNDP Project- Development of Growth Accounting Framework for Bhutan
Ministry of Finance and Keio Economic Observatory, (Ministry of Finance, Royal Government of Bhutan, and KEO, Keio University) ,
委員, 経団連 カーボンニュートラル行動計画第三者評価委員会
コンサルタント, 国連・アジア太平洋経済社会委員会 UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)
委員, 地球環境産業技術研究機構 イノベーション・投資促進検討ワーキンググループ
主査, 地球環境産業技術研究機構 経済分析ワーキンググループ
委員, 地球環境産業技術研究機構 地球温暖化対策国際戦略技術委員会