-
所属(所属キャンパス)
-
法務研究科(法科大学院) ( 三田 )
-
職名
-
教授
-
メールアドレス
-
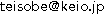
磯部 哲 ( イソベ テツ )
ISOBE Tetsu
|
|
|
日本学術振興会特別研究員(PD)
関東学園大学法学部専任講師
関東学園大学法学部助教授
獨協大学法学部専任講師
獨協大学法学部助教授
慶應義塾大学, 法学部, 法律学科
大学, 卒業
一橋大学, 法学研究科
大学院, 修了, 修士
一橋大学, 法学研究科
大学院, 修了, 博士
プラットフォームと社会基盤 : how to engage the monsters(怪獣化するプラットフォーム権力と法 Ⅳ巻)
磯部 哲, 河嶋 春菜, 慶應義塾大学出版会, 2024年10月
担当範囲: 「DPF時代の医療選択―私たちは何を信じ、どのように医療を選ぶのか」, 担当ページ: 114-137
Concilier santé et droits fondamentaux en période de pandémie Une analyse juridique des expériences de la France et du Japon
ギヨーム・ルセ, フィリップ・ペドロ, 磯部哲, 河嶋春菜 (担当:共編者(共編著者), Bruylant, 2024年04月
担当範囲: La politique vaccinale au Japon : vers un renouveau du respect de l'autonomie de la personne
看護をめぐる法と制度 (ナーシング・グラフィカ 健康支援と社会保障 4) 〔第5版〕
平林勝政=小西知世=和泉澤千恵=西田幸典編著, メディカ出版, 2024年01月
担当範囲: 医師法・あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律/柔道整復師法, 担当ページ: 91-106,160-164
磯部 哲, 河嶋 春菜, RoussetGuillaume, PédrotPhilippe, 尚学社, 2024年
担当範囲: 「医療従事者の職域―連携の確保に向けた法的仕組み」「まとめ 不確かな世界でパンデミックを考える」, 担当ページ: 211‐221,297‐301
条解行政事件訴訟法
南博方原編著,高橋滋,市村陽典,山本隆司編, 弘文堂, 2023年08月, ページ数: 254
医療に関する広告規制についての予備的一考察
磯部 哲
甲斐克則先生古稀祝賀論文集 下巻 医事法学の新たな挑戦 (成文堂) 423 - 438 2024年10月
Difficulties in ensuring review quality performed by committees under the Act on the Safety of Regenerative Medicine in Japan
Tsunakuni Ikka, Misao Fujita, Taichi Hatta, Tetsu Isobe, Kenji Konomi, Tatsuo Onishi, Shoji Sanada, Yuichiro Sato, Shimon Tashiro, Morikuni Tobita
Stem Cell Reports 18 ( 3 ) 613 - 617 2023年03月
磯部, 哲
Monsterizing Platform Power and Law ; Volume 4. Platforms and Social Foundations: How to Engage the Monsters (Keio University Global Research Institute) 69 - 82 2025年
磯部, 哲
Monsterizing Platform Power and Law ; Volume 4. Platforms and Social Foundations: How to Engage the Monsters (Keio University Global Research Institute) [1] - 12 2025年
Ikka T., Fujita M., Hatta T., Isobe T., Konomi K., Onishi T., Sanada S., Sato Y., Tashiro S., Tobita M.
Stem Cell Reports (Stem Cell Reports) 18 ( 5 ) 2023年05月
ISSN 22136711
Ikka T., Fujita M., Hatta T., Isobe T., Konomi K., Onishi T., Sanada S., Sato Y., Tashiro S., Tobita M.
Stem Cell Reports (Stem Cell Reports) 18 ( 3 ) 613 - 617 2023年03月
ISSN 22136711
法定受託事務に関する情報公開と国の処理基準
磯部 哲
別冊ジュリスト地方自治判例百選[第5版] (有斐閣) 34 - 35 2023年
混合診療
磯部 哲
別冊ジュリスト医事法判例百選[第3版] (有斐閣) 16 - 17 2022年
放送局免許拒否処分と訴えの利益
磯部 哲
別冊ジュリスト行政判例百選Ⅱ[第8版] (有斐閣) 344 - 345 2022年
医療安全理念に基づく事故調査と紛争解決―透明性とコミュニケーションの確保に向けて
科学研究費助成事業, 平野 哲郎, 松村 由美, 渡辺 千原, 松宮 孝明, 李 庸吉, 小西 知世, 磯部 哲, 米村 滋人, 小谷 昌子, 上向 輝宜, 中部 貴央, 佐和 貞治, 手塚 則明, 浦松 雅史, 基盤研究(B), 未設定
科学研究費助成事業, 米村 滋人, 磯部 哲, 奥田 純一郎, 山本 奈津子, 荻島 創一, 中山 茂樹, 水野 紀子, 徳永 勝士, 佐藤 雄一郎, 猪瀬 貴道, 基盤研究(B), 未設定
科学研究費助成事業, 小寺 智史, 磯部 哲, 岡田 希世子, 奈須 祐治, 高 史明, 成原 慧, 基盤研究(C), 未設定
西南学院大学, 科学研究費助成事業, 小寺 智史、磯部 哲, 岡田 希世子, 奈須 祐治, 鵜飼 健史, 高 史明, 挑戦的研究(萌芽), 未設定
テーマ演習
2025年度
研究会(法律学科)Ⅳ
2025年度
研究会(法律学科)Ⅲ
2025年度
研究会(法律学科)Ⅱ
2025年度
研究会(法律学科)Ⅰ
2025年度
日本公法学会,
日本医事法学会,
日仏法学会,
ローマ教皇庁(ヴァチカン)生命アカデミー,
医学系大学倫理委員会連絡会議,
防衛人事審議会委員
東京都動物愛護管理審議会委員
医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会委員
国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会委員
厚生労働省社会保障審議会専門委員(小児慢性特定疾病対策部会委員、小児慢性特定疾対策委員会委員)