-
所属(所属キャンパス)
-
環境情報学部 慶應SFCスペイン語・スペイン語圏研究室/SFC Kotan―アイヌ語アイヌ語口承文学研究室 ( 湘南藤沢 )
-
職名
-
専任講師
-
メールアドレス
-
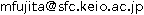
-
研究室住所
-
湘南藤沢キャンパスλ403(個人研究室)、λ401(スペイン語・スペイン語圏共同研究室)
藤田 護 ( フジタ マモル )
FUJITA, Mamoru
|
|
|
アビヤ・ヤラ(ラテンアメリカ)の特にアンデス地域とヤウン モシㇼ(北海道)を行き来しながら研究を続けています。これらの地域の先住民言語であるアイマラ語、ケチュア語、そしてアイヌ語が、現代に生き続けられているその取り組みに実際に関わりながら、それらの言語の口頭で伝承される物語の世界が伝える複雑な世界を探求しています。コリャスーユ(ボリビア)とペルーを中心としたラテンアメリカで先住民が政治や開発とどのように関わってきたのか、ラテンアメリカや日本で文字で書かれた文学が口承文学とどのように関わってきたのかといった問題も考え続けています。学生たちとケチュア語(ペルー、ボリビア)やバスク語(フランス南部、スペイン北部)の勉強会をしたり、スペイン植民地時代に残されたケチュア語の神話の記録(『ワロチリ文書』)を読む市民講座を続けてもいます。
もっと広く深い多言語・多文化の世界へ
Let us always maintain a sense of deep crisis and a stance of critical commitment.
アンデス・オーラルヒストリー工房(Taller de Historia Oral Andina, THOA), (ボリビア・ラパス市のアイマラ先住民団体), 外部協力者
アジア太平洋資料センター(PARC)自由学校, 講師・企画委員・「クラブ活動」主任(「Club Andino-先住民言語を通して南米アンデスの文化を学ぶ」)
神奈川大学外国語学部, スペイン語学科, 非常勤講師
外務省, 在ボリビア日本国大使館, 専門調査員(政務・経済担当)
国際協力機構(JICA), 客員研究員(アンデス高地先住民への協力)
日本学術振興会, 特別研究員(DC2)
ボリビア外務省多民族外交アカデミー, 客員研究員
東京大学, 教養学部スペイン語部会(前期課程)/ラテンアメリカ科(後期課程), 教務補佐員(助手)
東京大学, 大学院総合文化研究科, 地域文化研究専攻(小地域:中南米)
大学院, 単位取得退学, 博士後期
サセックス大学大学院, 国際開発研究所, M.Phil. in Development Studies
グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国), 大学院, 修了, 修士
東京大学, 教養学部, 教養学科第二(主専攻:中南米の文化と社会、副専攻:国際関係論)
大学, 卒業, その他
人文・社会 / 地域研究 (ラテンアメリカ研究(特にアンデス社会))
人文・社会 / 日本文学 (日本近現代文学(特に大江健三郎と津島佑子))
人文・社会 / 言語学 (アイヌ語・アイヌ語口承文学研究)
人文・社会 / 外国語教育 (スペイン語教育)
人文・社会 / 国際関係論 (開発研究、国際開発協力研究(特に開発の人類学))
日本から考えるラテンアメリカとフェミニズム
水口良樹, 柳原恵, 洲崎圭子, 中南米マガジン, 2025年03月, ページ数: 162
担当範囲: ボリビアの先住民女性の声とフェミニズム, 担当ページ: 71-73
世界の昔話を知るために!
石井正己編, 三弥井書店, 2025年01月, ページ数: 268
担当範囲: 「南米アンデス高地アイマラ語の物語世界」, 担当ページ: 102-109
明石書店, 2025年01月
担当範囲: 第10章「アイマラとウルーアンデス高地の先住民」、第14章「貧困と格差―新時代の政策議論と残り続ける構造的問題のあいだで」、第49章「インディヘニスモからインディアニスモへ―ボリビアの先住民運動と政治思想」、第50章「ナショナリズムから多民族国家へ―ボリビアの政治思想と国家形成」、第51章「ボリビアの文学―社会と政治と結びつきながら躍動する文学の世界へ」、第52章「ボリビアの映画―ウカマウ映画の「後」へ」、第53章「先住民の口承文芸―「物語」と「歴史」の枠を超えて展開する語りの世界」
桑原武夫、清水唯一朗編著, 慶應義塾大学出版会, 2023年02月
担当範囲: 第10章「『よく生きる(ブエンビビール)』という理念を問い直す――先住民の言葉と視点から何を学ぶことができるか」、執筆者鼎談、巻末ブックガイド
(近刊)金成マツ筆録ノートのアイヌ語口承文学テクストの原文対訳及び解釈――金田一京助宛ノート散文説話「一人の頭の禿げた白いかさぶたがフケになっている女性がくにの上手からやって来るウェペケㇾ(sine esukopitce retar cima koeyanrasne menoko mosir pa wano ek uepeker)」
藤田護
千葉大学ユーラシア言語文化論集 (千葉大学ユーラシア言語文化論講座) 27 2025年12月
研究論文(大学,研究機関等紀要), 単著, 筆頭著者
(近刊)金田一京助記録「ユーカラ・ノート」における鍋沢コポアヌ口述のエゾイタチ(upas cironnup)に関する散文説話2編
藤田護
千葉大学ユーラシア言語文化論集 (千葉大学ユーラシア言語文化論講座) 27 2025年12月
研究論文(大学,研究機関等紀要), 単著, 筆頭著者
近年の南アンデス・ケチュア語口承文学におけるテクスト公刊とその「読み」の可能性
藤田護
アンデス・アマゾン学会研究発表要旨集 (アンデス・アマゾン学会) 14 23 - 24 2025年11月
単著, 筆頭著者
 藤田護(2025)「近年の南アンデス・ケチュア語口承文学におけるテクスト公刊とその「読み」の可能性」【アンデス・アマゾン学会研究発表要旨集』14
藤田護(2025)「近年の南アンデス・ケチュア語口承文学におけるテクスト公刊とその「読み」の可能性」【アンデス・アマゾン学会研究発表要旨集』14
Carmen Belén García Bernal, Verónica Prieto, Mayuko Ogura, Rie Takabatake, Mamoru Fujita
慶應義塾外国語教育研究 (慶應義塾大学外国語教育研究センター) 21 1 - 25 2025年09月
研究論文(大学,研究機関等紀要), 責任著者, 査読有り
知里幸惠『アイヌ神謡集』を読み直す――脱植民地化をめざして
藤田護
社会文学 (日本社会文学会(不二出版)) 62 20 - 34 2025年08月
研究論文(学術雑誌), 単著, 筆頭著者, ISSN 09140042
藤田, 護
慶應義塾外国語教育研究 (慶應義塾大学外国語教育研究センター) 21 1 - 25 2024年
地域研究と応用言語学とのあいだで : スペイン語の/からの越境
藤田, 護
Keio SFC journal (慶應SFC学会) 24 ( 2 ) 28 - 35 2024年
ISSN 13472828
SFCにおける多言語多文化社会構築に向けた高大接続のスペイン語教育 : コロナ禍の下でのカリキュラム改革の経験
藤田, 護
慶應義塾外国語教育研究 (慶應義塾大学外国語教育研究センター) 19 99 - 123 2022年
ラテンアメリカの多文化主義政策と日本の防災教育ワークショップの交わる地点で : メキシコとペルーにおける災害認識とナラティブ、コミュニケーターの役割、先住民知と近代科学技術の関わり
藤田, 護
Keio SFC journal (慶應SFC学会) 21 ( 2 ) 144 - 167 2021年
ISSN 13472828
巻頭言 : 新しい批判的多言語主義と多言語教育への含意 : SFC/慶應における実践から
藤田, 護
Keio SFC journal (慶應義塾大学湘南藤沢学会) 19 ( 2 ) 6 - 19 2019年
ISSN 13472828
Releer y revalorar la historia oral de las mujeres
FUJITA, Mamoru
La Prensa (La Paz, Bolivia) 2025年06月
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア), 単著, 筆頭著者
文学の形態で呼び戻される/読み直される戦争裁判(書評――金ヨンロン著『文学が裁く戦争――東京裁判から現代へ』岩波新書、2024年)
藤田 護
越境広場 (越境広場刊行委員会) 14 170 - 172 2025年03月
書評論文,書評,文献紹介等, 筆頭著者
藤田護
朝日新聞(耕論「価値観の更新、エンタメでは」) (朝日新聞社) 13 - 13 2024年08月
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア), 単著, 筆頭著者
藤田護
Fieldnet(オンライン) (東京外国語大学アジア・アフリカ研究所) 2024年01月
記事・総説・解説・論説等(その他), 単著, 筆頭著者
FUJITA, Mamoru
[国際会議] First Glocal Conference on Quechua Languages and Cultures (University of Pennsylvania) ,
口頭発表(一般), Penn Language Center and the Programa de Lengua y Cultura Quechua (University of Pennsylvania), Red de Estudios Indígenas Globales de la Hamilton Lugar School of Global and International Studies (Indiana University in Bloomington)
藤田護
[国内会議] 第25回ラテンアメリカ研究講座「先住民と移民の事例から見る継承語――消えゆく言葉と伝える言葉」 (京都市) ,
公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等, 京都外国語大学ラテンアメリカ研究センター
 口承文芸と言語継承――アンデス高地の現場から (京都外国語大学12月20日)※12月21日(日)YouTubeリンク修正
口承文芸と言語継承――アンデス高地の現場から (京都外国語大学12月20日)※12月21日(日)YouTubeリンク修正
『長濱清蔵のアイヌ語』刊行の意義とこれから
藤田護
[国内会議] 北海道博物館講演「『長濱清蔵のアイヌ語』を刊行して」 (札幌市) ,
公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等, 北海道博物館
Aynu Language and Museum Exhibitions
FUJITA, Mamoru
[国際会議] IV International Conference on the Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages (京都市) ,
シンポジウム・ワークショップ パネル(公募), 京都大学
近年の南アンデス・ケチュア語口承文学におけるテクスト公刊とその「読み」の可能性
藤田護
[国内会議] アンデス・アマゾン学会第14回大会 (tdi人材開発センター湯河原) ,
口頭発表(一般), アンデス・アマゾン学会
南米アンデスと北海道アイヌ語の口承文芸と言語復興を繋ぐ
日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
長濱清蔵のアイヌ語――十勝地方の物語
藤田 護, 研究成果公開促進費(学術図書), 補助金, 研究代表者
南米アンデス南部高地の言語多様性と口承の語り
日本学術振興会, 科研費基盤(C), 藤田護, 補助金, 研究代表者
多言語多文化社会構築に向けた高大接続のスペイン語教育
日本学術振興会, 科研費基盤研究(C), 小倉麻由子、高畠理恵、カルメン・ガルシア、ベロニカ・プリエト、齋藤華子、遠藤杏、西村亜希子, 補助金, 研究分担者
日本・アイヌ語及び南米アンデス・アイマラ語の口承テクストの回復・公刊と分析
文部科学省・日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 藤田 護, 基盤研究(C), 補助金, 研究代表者
<資料公開>金成マツ筆録ノートの口承文学テクストの原文対訳(1) ――知里真志保宛ノート散文説話「六人の山子(iwan yamanko)」――
藤田 護
その他, 単独
〈書評〉清水透『ラテンアメリカ: 歴史のトルソー』立教大学ラテンアメリカ研究所、2015年、220p.
イベロアメリカ研究 37(2), 61-64,,
その他
地域と社会(米州)(SFC先端科目)
2020年度, 春学期, 講義, 専任
アイヌの言語と文化(SFC先端科目)
2020年度, 秋学期, 講義, 専任
アカデミックプロジェクト(AP)「多言語多文化共生社会」
2020年度, 通年, 演習, 兼担
研究会B(1)「『南』からの思考(スペイン語圏の社会と多言語主義の研究)」
2020年度, 通年, その他, 演習, 専任
研究会B(2)「SFC kotan―アイヌ語の現在とアイヌ語の口承の物語の世界へ 」
2020年度, 通年, 演習, 専任
クルブ・アンディーノー先住民言語を通して南米アンデスの文化を学ぶ(現在まで継続中)
アジア太平洋資料センター(PARC)自由学校
通年, 演習, 専任
ワロチリ文書、ケチュア語、アイマラ語、植民地期ラテンアメリカ
現代文化論/アイマラ語とアンデス文化(学部大学院合併科目)
東京大学大学院人文社会系研究科
秋学期, 講義, 専任
ラテンアメリカ概論(2019年度まで担当)
神奈川大学外国語学部スペイン語学科
通年, 講義, 専任
現代のラテンアメリカ(2017年度まで担当)
関東学院大学国際文化学部
春学期, 講義, 専任
南米研究入門(2017年度まで担当)
関東学院大学国際文化学部
秋学期, 講義, 専任