-
所属(所属キャンパス)
-
経済学部 ( 三田 )
-
職名
-
教授
-
メールアドレス
-
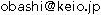
小橋 文子 ( オバシ アヤコ )
OBASHI Ayako
|
|
国際貿易と貿易ルール・制度の研究を専門とする経済学者です。国境を越えた企業の生産活動、つまり、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)をめぐる諸問題に関心を寄せて研究しています。2011年に慶應義塾大学より最初の博士号を取得し、2018年にウィスコンシン大学マディソン校より2つ目のPh.D.を取得しました。慶應義塾大学経済学部助教(研究)、東洋大学経営学部助教、青山学院大学国際政治経済学部助教そして准教授を経て、2023年4月より現職。
慶應義塾大学, 経済学部, 助教(研究)
東洋大学, 経営学部, 助教
青山学院大学, 国際政治経済学部, 助教
青山学院大学, 国際政治経済学部, 准教授
慶應義塾大学, 経済学部, 教授
慶應義塾大学, 総合政策学部
大学, 卒業
慶應義塾大学, 経済学研究科
大学院, 修了, 修士
慶應義塾大学, 経済学研究科
大学院, 単位取得退学, 博士
ウィスコンシン大学マディソン校, 経済学部
アメリカ合衆国, 大学院, 修了, 博士
修士(経済学), 慶應義塾大学, 2008年03月
博士(経済学), 慶應義塾大学, 2011年05月
Ph.D. , ウィスコンシン大学マディソン校, 2018年12月
UNCTAD Certified Non-Tariff Measures Data Collector Certificate, 2015年07月
不確実性とFDI : 企業戦略への影響を探る
法政大学比較経済研究所, 倪, 彬, 日本評論社, 2025年03月, ページ数: x, 205p
担当範囲: 第7章 国境拒否リスクと企業の輸出行動
国際貿易論の包絡線 = The envelope of international trade studies
木村 福成 , 清田 耕造 , 安藤 光代, 小橋 文子, 慶應義塾大学出版会, 2025年, ページ数: iv, 257p
Trade in goods with internationalised production activities
Matsuura T., Obashi A., Handbook on East Asian Economic Integration, 2021年01月
Non-Tariff Measures in Australia, China, India, Japan, New Zealand and the Republic of Korea: Preliminary Findings
Kaoru Nabeshima, Ayako Obashi, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2020年09月
担当範囲: Chapter 5 Non-Tariff Measures in Japan, 担当ページ: pp. 45-54
Production Networks and Enterprises in East Asia: Industry and Firm-level Analysis (ADB Institute Series on Development Economics)
Fukunari Kimura, Ayako Obashi, Springer Japan, 2015年12月, ページ数: XIII, 326
担当範囲: Chapter 3: Production Networks in East Asia: What We Know So Far, 担当ページ: pp. 33-64
Exploring Pathways for Deeper Regional Cooperation in ASEAN and East Asia
Kaoru Nabeshima, Ayako Obashi, Kunhyui Kim
Journal of Southeast Asian Economies (ISEAS – Yusof Ishak Institute) 42 ( 3 ) 241 - 260 2025年12月
研究論文(学術雑誌), 共著, 査読有り, ISSN 23395095
Global Warming and Border Carbon Adjustments
Hong S., Sim S.G., Obashi A., Tsuruta Y.
Asian Journal of Law and Economics (Walter de Gruyter GmbH) 13 ( 2 ) 195 - 208 2022年08月
査読有り
Technological advancement, import penetration and labour markets: Evidence from Thailand
Jongwanich J., Kohpaiboon A., Obashi A.
World Development (Elsevier BV) 151 ( 105746 ) 105746 - 105746 2022年03月
査読有り, ISSN 0305750X
Ando M., Kimura F., Obashi A.
Asian Economic Papers (MIT Press - Journals) 20 ( 3 ) 40 - 72 2021年11月
査読有り, ISSN 15353516
Impacts of additional compliance requirements of regulations on the margins of trade
Nabeshima K., Obashi A., Kim K.
Japan and the World Economy (Elsevier BV) 59 ( 101088 ) 101088 - 101088 2021年09月
査読有り, ISSN 09221425
日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 鍋嶋 郁, 道田 悦代, 雷 蕾, 小橋 文子, 大槻 恒裕, 金 健輝, 道田 悦代, 雷 蕾, 小橋 文子, 大槻 恒裕, 金 健輝, 基盤研究(B), 研究分担者
日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 石川 城太, 阿部 顕三, 大久保 敏弘, 小橋 文子, 加藤 隼人, 木村 福成, 趙 来勲, 古澤 泰治, 椋 寛, 阿部 顕三, 大久保 敏弘, 小橋 文子, 加藤 隼人, 木村 福成, 趙 来勲, 古澤 泰治, 椋 寛, 基盤研究(S), 研究分担者
日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 鍋嶋 郁, 小橋 文子, 道田 悦代, 雷 蕾, 小橋 文子, 道田 悦代, 雷 蕾, 基盤研究(C), 研究分担者
IT化と国際化が企業ダイナミクスに与える影響:日中韓の企業の比較分析
日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 乾 友彦, 児玉 直美, 小橋 文子, 金 榮愨, 権 赫旭, 児玉 直美, 小橋 文子, 金 榮愨, 権 赫旭, 基盤研究(B), 研究分担者
令和3年度(第16回)小島清賞 優秀論文賞
2021年10月, 日本国際経済学会, 「技術規制と企業の輸出活動:日本の製造業企業の実証分析」(『国際経済』71巻、2020年)
国際経済論演習
2025年度
研究会d
2025年度
研究会c
2025年度
研究会b
2025年度
研究会a
2025年度
日本国際経済学会,
日本経済学会,
American Economic Association,